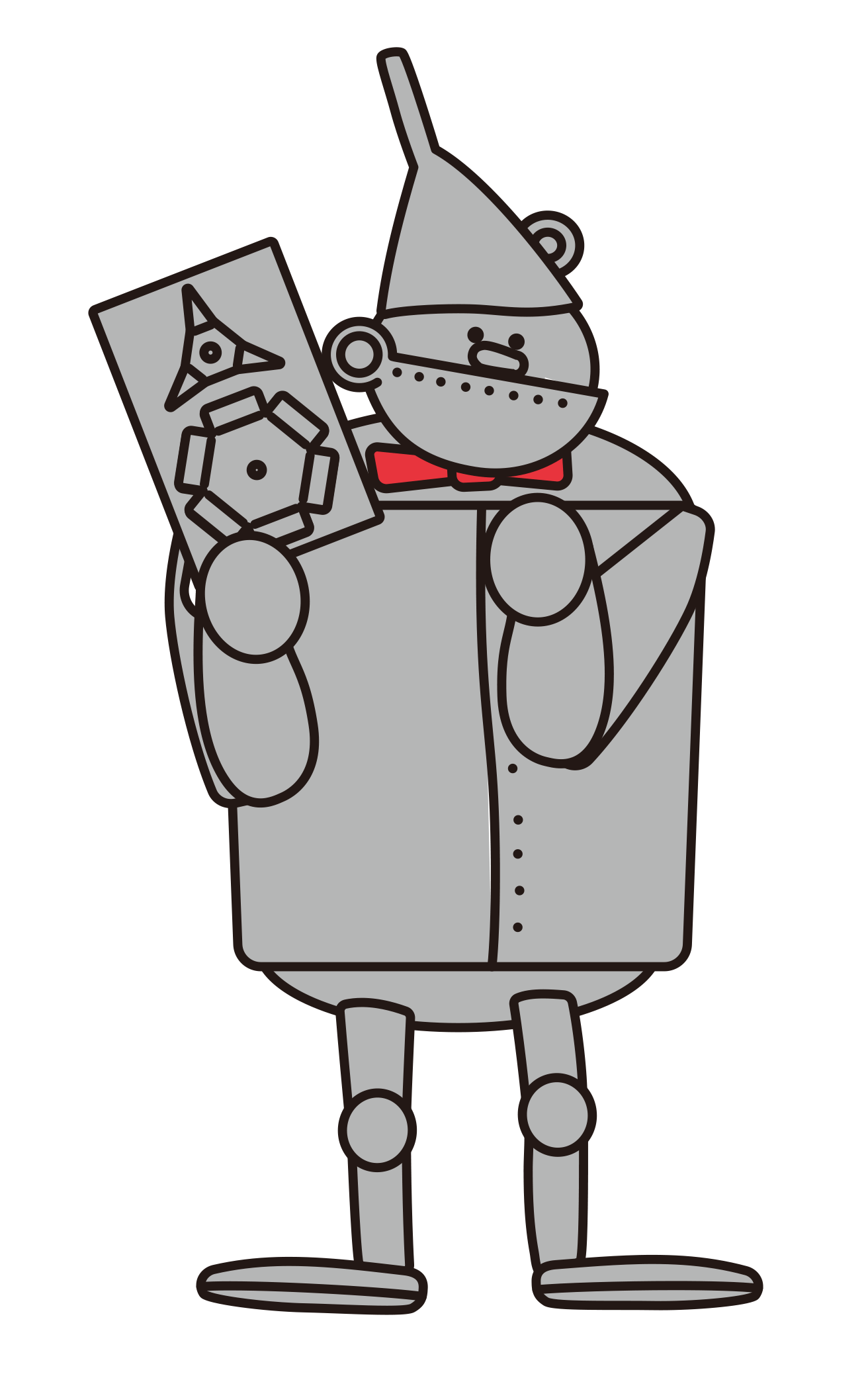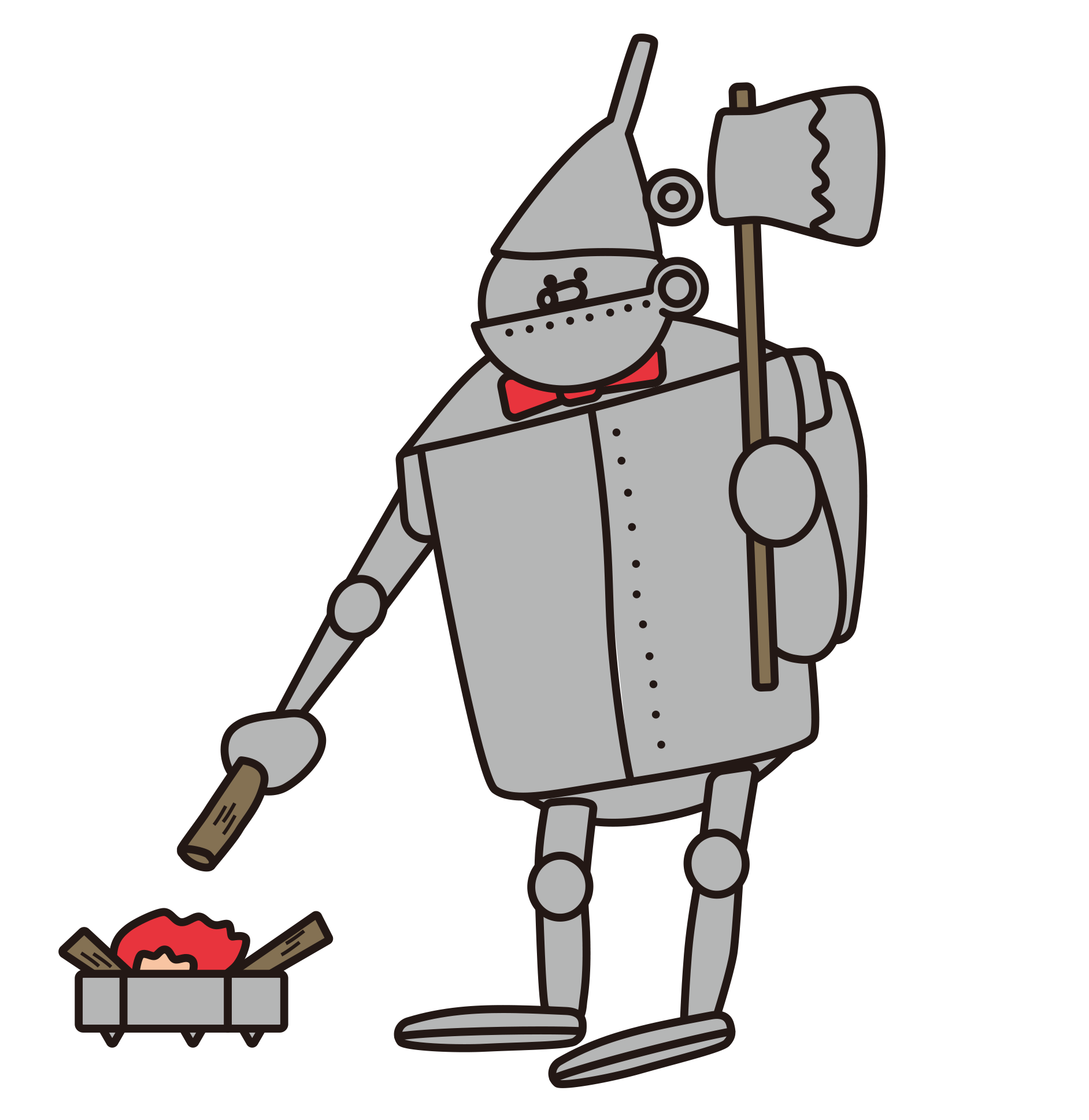top of page


けんきゅう
研究がしたい!

研究_歴史と役割
研究_焚き火台は燃えない
燃え方が違う
かならずまもってね
・火をつかうときは、かならず大人のひといっしょに。
・こどもだけで火をおこしたり、たき火をするのはすごくあぶない。
・火事になったり、だいじなものがもえちゃうこともあるよ。
・ぜったいに子どもだけで火を使ったらいけないよ。
※保護者の方へ
当サイト内の情報の利用は、お客様の責任において行ってください。
本サイトの情報は公開時のものであり、最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
たき火を行う際は、その場所のルールを守って実施してください。
 |  |  |  |
|---|
bottom of page